ジョヴァンニ・セルカンビ(Giovanni Sercambi)の『イル ノヴェッリエーレ(短篇集)』について
~地方都市の文学の運命~
米山 喜晟
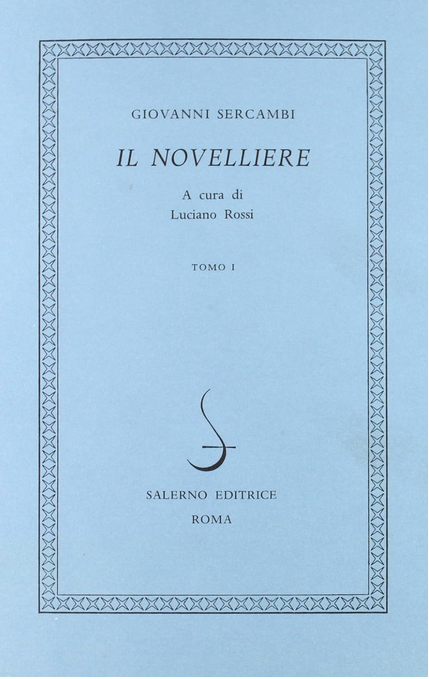
第1章 作者とその評価の問題点
a. G.セルカンビの生涯と作品
先ず作品の生涯を簡単に振返って見ると①、彼ジョヴァンニ・セルカンビは1348年のペストの最中に、ルッカで生れた。父はセル・イアコポ・ディ・セル・カンビオという薬屋で、その先祖はセル・イアコポ・ダ・インセーニャというマッサローザ出身の公証人であるといわれる。セル・イアコポは公証人で、14世紀初頭にルッカに移住し、その息子で、やはり公証人であったセル・カンビオから一族の姓が生じたとされている。そのセル・カンビオの息子が薬屋のセル・イアコポで、ジョヴァンニの父親である。すなわちルッカに移ってからまだ4代目にすぎず、その意味では新参者であり、成上り者(parvenu)という形容に値するであろう。しかし移住以前の社会的身分や資産などが明らかでない以上、このことから余りにも多くの想像にふけることは許されない。作品の内容と相まって彼の文学が小市民の文学の典型のごとく見なされる傾向があるが、私は大いに疑問の余地があると考えている。
① この部分は主に本文第1章 a の末尾で記した二つの版に収められた Nota Bio-Bibliografica(di G. Sinicropi)と Nota Biografica (di L. Rossi)によっている。
幼少期に受けた教育についても、彼を直接教えた教師たちの名前がいろいろと想定されているが、実際には具体的なことはほとんどわかっていないようである。ただし、当時のルッカの教育水準が決して低くはなく、何人かのすぐれた教育者が存在していたことは確実で、彼がそうした便宜を利用しやすい立場にあったことも否定できない。いずれにせよ彼は大学教育は受けておらず、ラテン語の知識などは私塾のような所で学んだと推測できる。また彼は当時の習慣に従って20才以前に母方の一族である Campori 家から、おそらく彼よりも年長の女性と結婚したが、その持参金は800フィオリーノ② 以上であったとされている。この800フィオリーノという金額は、たとえばフィレンツェのピッティ家の例など比較しても、決して少ないとはいえない。勿論様々な事情もあっていちがいには言えないにしても、セルカンビがこれ程高額の持参金を伴う結婚をしていること自体、彼を小市民の典型のごとく見なす見方を困難にしている。
② Nota Biografica, op. cit.. p.LXII.
彼の父が1370年ごろに死んだため、セルカンビは20才そこそこで薬屋の店を継いだが、この点も誤解されやすい。この当時の薬屋は、今日のように主に医薬品のみを扱っていたのではない。勿論医薬品、薬草、そして砂糖菓子の類も大いに扱ってはいるが、それ以外に文房具品店をも兼ねていて、インク、ペン、封蝋、羊皮紙、また当時普及しつつあった今日の紙類をも販売していた。さらには手稿、写本つまり書物そのものをも扱っていたのである。R.A.Prattなどは、セルカンビの文学活動の機縁をまさにこの書物の売買そのものの内に見出そうとしている程である③。後でも指摘するが、この薬屋という職業の影響は、『イル・ノヴェッリエーレ』の中にも反映している。
③ R. A. Pratt, Giovanni Sercambi, Speziale, in "Italica", 1948XXV, pp.12-14.
ところが、彼は必らずしもその商売に専念していたわけではないらしい。LXXIVに、叔父と共にフィレンツェに仕入れに行った経験なども描かれているので、多少の経験は積んでいた筈だが、「父ゆずりの薬屋の店は、おそらくより熟練した他人の手にまかした」④ というのが実情で、早くも1372年に、24才という若さで、共和国議会(il Consiglio Generale della Repubblica )」の議員となり、その後一貫して、市政に参加し続けているのである。
④ 注① の Nota Bio-Bibliografica op. cit., P.762.
ここで簡単にルッカという一地方都市が14世紀にどのような政治的状況におかれていたかを振り返ると、先ず軍事的天才カストルッチオ・カストラカーニが1316年にその終身領主となって、フィレンツェを脅したことが注目される。しかし、1328年のこの領主の死と共に彼の領地は一挙に崩壊してしまい、その中心にあったルッカそのものの領主権すら、一時期宙に浮いてしまって、ドイツ人の傭兵軍、ジェノヴァのスピノーラ家、ジョヴァンニ・ディ・ボエミア、パルマのロッシ家、ヴェローナのスカリジェーリ家などの間を、まるでフットボールのように転々と往復する。勿論その背後では、フィレンツェとピサという近隣の二大勢力が、この要地を獲得するために執拗な努力を重ねていて、結局1342年7月にはピサの勢力下に落着く。その結果に失望した余り、フィレンツェでは同年の9月にアテネ公の独裁制が採用されるというおまけがついた。
この時にピサとルッカとの間で結ばれた条約は、一見平等かつ対等の同盟条約のごときもので、ルッカの独立は保障されており、フィレンツェその他の外敵に対して攻守両面における共同戦線を規定したものにすぎなかったが、実際には、ピサはルッカに対して「真の隷属」⑤ を課したとされている。その条約締結後6年目に生れたセルカンビはピサのくびきから逃れようとする市民の努力を目前にしつつ育ったわけである。
⑤ Augusto Mancini, Storia di Lucca, Firenze 1950, p.153.
1357年に15年間の期限が切れた後も、ピサの支配は終らず、1362年に公式に宣言されたピサとフィレンツェとの戦争(すでに何年も前から戦闘状態は続いていた)にも、ルッカは当然ピサと協力してフィレンツェと戦っている。ところがそのピサ自体も政権はほぼ恒常的に不安定で、フィレンツェとの戦いの失敗が、一時期デッラニェッロ家の独裁をもたらしている。皇帝カール四世の南下と共に(1368年8月)、ピサでは紛争が激化し、デッラニエッロ家の支配は終り、コムーネ制に戻るが、ルッカはこの好機を捕えて、皇帝の好意にすがり、約30年続いたピサの支配下から脱する。ただし、「ルッカの解放は反乱や民衆の運動によるものではなくて、皇帝の意志のみによって生じた」⑥ のだ。
⑥ ibid., P.163.
セルカンビはこの時まだ20才そこそこであったにもかかわらず、友人 Davino Castellani と共に皇帝への使節に赴き、コムーネの名で詩を献じたと記録されており、早くから市政に熱意を燃やしていたことが分る。また城砦の引き渡しの際にも市民兵の1人として加わっている。その後ピサが弱体化したり、フィレンツェでも政情不安が続いた(1378年のCiompi の反乱など)せいで、ルッカはこの二大勢力の支配をまぬがれて数十年におよぶ自治を享受したが、その前半はゴンファロニエーレ・ディ・ジュスティツイアと数人のアンツィアーノを主体とする民主政体、後半はグィニージ家の独裁下にあった。
すでに見た通りセルカンビは24才で民主制下の議会のメンバーとなり、1381年以降は「36人委員会」のメンバーになるとともに、外交使節として兇暴な傭兵隊長アルベリーゴ・ダ・バルビアーノ伯と交渉し、その被害が市に及ぶのを防ぐなど(1381年、その兵士の暴行については「第七十六話」が記述)の功績もあった。しかしルッカの民主政体は、ちょうど半世紀後のフィレンツェにおけるメディチ家にも比較しうるような、抜群に富裕なグィニージ(Guinigi)家の擡頭によって危機にさらされる。
元来ピサは絹織物の産地として栄え、その技術水準の高さを誇っていたが、グィニージ家も絹織物業を営むと共に、両替商兼金融業者として巨富を蓄え、特にフランチェスコはあたかもコーシモ・ディ・メディチのごとく、すぐれた手腕を発揮し、イタリア国内のみならずブルージュやロンドンにも支店を持つ両替業者および教皇庁の収税人として活躍した。彼の存命中は、ちょうどコーシモの場合と同様、一応民主政体を尊重して、背後から思いのままに市政を牛耳つていたが、1384年に彼が死ぬと、一時期権力の主体が失われ、やがてフォルテグェルリ家を主体とする反対派が主導権を握る。しかし Forteguerra Forteguerri が、1392年5月にゴンファロニエーレに選出されると、グィニージ派の不安は頂点に達し、同年5月12日グィニージ派の与党は聖ミケーレ広場に集合して、ゴンファロニエーレの軍隊を撃破し、フォルテグェッラ自身をも殺害して、権力を奪回してしまい、フランチェスコの息子ラッザロ・グィニージが市政の中心に座る。
ほぼこの時期から、セルカンビの死後までグィニージ家の独裁が続いたと見なすことは可能だが、なお暫く民主政体の形式は維持された。なお セルカンビ がこの一派の有力な協力者であったことは、同年の9~10月のアンツィアーノに選ばれていることから見て明らかである。セルカンビは生涯にアンツィーノに2度、ゴンファロニエーレに2度就任して、一応民主政体の頂点を極めるわけだが、いずれもこの内乱以後のことであり、反対派の没落によって一挙に浮上したという印象は否みがたい。
ところがさらに1400年2月、ラッザロは弟アントニオによって暗殺され、アントニオも処刑されるという突発事件が生じ、ペストで一族が人材を失っていたという事情もあって、当時24才のパオロ(1376~1432)がラッザロの地位を継ぐが、もはや民主政体という擬制を維持する余力は失われたのであろうか、1400年10月13日の夜半、パオロは大権委員会を召集して市の独裁権を要求、何の抵抗も受けずに一挙にルッカの領主となった。ところがこの筋書を書いたのは、まさにこの時期にゴンファロニエーレであったセルカンビであったといわれ、そのため死後は「民主的自由の敵」⑦ という烙印を押されねばならなかった。
⑦ Nota Bio-Bibliografica, op. cit., P.766.
その後のセルカンビはやはり数々の役職につき、顧問の1人として重んじられ、1424年3月27日に没した時も、公費によって葬られた。もっとも彼の『年代記』の中には、「ルッカのジョヴァンニ・セルカンビがグィニージ家および領主パオロ・グィニージの友人であったために受けた損害」⑧ という一章があって、政敵からの襲撃や店への放火などいう損害はゆうに1万フィオリーノに及ぶと計算している。しかしこうした記述は、不満のためというよりは、他の市民の羨望に対する弁明と見た方が正しいようで、事実彼は市庁関係の文房具の独占的な業者として結構かせいでいたように思われる。
⑧ G. Sercambi, Croniche, Vol. III, a cura di G. Bongi, Roma, 1892, pp.333-48.
ところでパオロ・グィニージの独裁制そのものも、その外交的判断の誤りのために1428年には崩壊しており⑨、同時に12人大権委員会によって旧来の民主制が再建されている。この政変は、セルカンビの死後の評判や作品の保存にとって勿論不利に作用した筈である。
⑨ A. Mancini, op.cit., pp.195-197.
なおセルカンビには本書の他に、1392年から1400年の間に書かれたと思われる『グィニージ家の諸君に与える覚え書(Nota a voi Guinigi)⑩』およびセルカンビが20才の時に書き始め、1423年7月まで書き及んだ、1164年以降の『ルッカ年代記』⑩ という著書がある。『年代記』は第1部と第2部とから成り、彼自身の政治体験に裏付けられた貴重な地方都市の政治的記録として評価され、すでに前世紀にすぐれた版が刊行⑪ されており、彼の政治的素質を文学的なそれ以上に評価する見方すらある。
⑩ G.Sercambi, Croniche, op.cit., Vol.III pp.397-407 に所収。
⑪ 注⑧ 参照。
最後に彼のノヴェッラ集については、『デカメロン』同様100篇のノヴェッラから成り立っていたバローニ本(ルッカ人ベルナルディーノ・バローニが所有していたといわれる)なるものが存在したことも知られているが、今日はすでに残っておらず、我々が読み得るのは序文と155のノヴェッラ(その前に短い文章がつく)とで成り立つ写本トリヴルツィアーノ193にもとづく作品集のみである。一時は『デカメロン』、サッケッティの『三百話』、『ペコーネ』に次ぐ、14世紀における第四位のノヴェッラ集⑫ という評価さえ受けていた程の本書だが、その完本はなかなか手に入りにくかったらしい。幸い近年に2つのいくらか差異はあるが。いずれも極めて良心的な版本が刊行されて、我々も容易にその全貌を知ることができることとなった。その1つはシニクローピの校訂によるもの(A cura di Giovanni Sinicropi, Bari 1972、因みにこの版は “Novelle" という標題を付して、バローニ本と区別している)と、他の1つはロッシによるもの(A cura di L. Rossi, Roma 1974)である。本論は主に後者にたより、標題もその版に従った。
⑫ Luigi Russo, Ser Giovanni Fiorentino e Giovanni Sercambi, in "Belfagor" XI(1956), pp.489-504.
b. 本書への評価をめぐって
ところで本書に対する評価は、率直に言ってそれ程かんばしいものとはいえない。たとえば第二次大戦以前のイタリアで最も高い権威を誇った文学批評の大御所 B.クローチェ(Croce)は、その著『民衆詩と芸術詩』の中で、ボッカッチオとセルカンビとの関係について述べたが、それはこの作者がボッカッチオから本質的なものは何一つ学んでいないことを示す酷評であった。「…セルカンビは、想像力の組合せをさらにだらしなく怠惰に踏襲し、それ以前もしくは伝統的な形式の中でそれらの物語が持っていたあらゆる意味をしばしば取除いてしまい、おまけに下品なやり方で卑猥さに溺れてしまう。⑬」
⑬ B. Croce, Poesia popolare e poesia d'arte, Bari, 1967, P.95.
またB. クローチェとは著るしく立場を異にして、しばしば批判的だったと思われる、戦後の代表的な文学史家サペーニョ(N. Sapegno)も、先ずセルカンビのことを「あの領主政権の主要な援護者の1人であり、ラッザロそして後にパーオロ・グィニージに意見を求められた助言者であり、その有能な協力者であった(中略)ジョヴァンニ・セルカンビ」⑭ という彼一流の長文でその批評を始めているが、「(『ペコローネ』と比較した場合)はるかに表現力が劣り、粗野で、いく分無器用なのがセルカンビで、彼において先ず、ボッカッチオの世界の最も外面的で、単なる内容的側面へのあの堕落(それはその後の2世紀間により公然と推進されるだろう)が実現されるのだが、その場合にしばしばつきまとうのは鈍重な趣味であって、好色さとか卑猥さから詩的に解き放たれることは全くない」⑮ とまさに酷評を下すのである。
⑭ N. Sapegno, Storia letteraria del trecento, Milano-Napoli. 不明. P.357.
⑮ ibid.
以上は今世紀の大御所たちの見解だが、もう少し長期間におけるセルカンビ批評の変化を概観した便利な一文があるのでそれを引用しておきたい。
「セルカンビに対して批評の注意が払われたのは比較的最近である。『ノヴェッリエーレ』に対する肯定的な評価は Lucchesi から Minutoli にかけてかなりの研究者によって反復されており、やがて全作品にはじめて目を通した Gamba の権威にもとづいた D'Ancona に至っている。また未刊だった分のノヴェッラを公刊した Renier によっても〈価値ある作者〉セルカンビの神話は傷つけられなかった。セルカンビの作品が『デカメロン』からの卑俗な借り物であることを最初に告発したのは Gaspary で、その後直ちに Torracca、Zenatti などがそれに続いた。Rossi、 Volpi、 Di Francia のような後代の研究者たちも、資料を豊富に蒐集している点で作品の価値をみとめてはいるものの、その芸術的価値の乏しさを強調した。美学的非難に加えて、道徳的非難が Croce、 Sapegno、Floraらによって繰り返された。
Chiariの評価もそれ以上に肯定的なものではなかった。彼は民話的および喜劇的ジャンルのいくつかのノヴェッラを嫌いはしなかったが、主題の持つ不愉快な下品さと、年代記的、外面的性格を強調した。また Muscetta の評価も、この作品がいつかの小話で物語としての立派な成果を達成したことを認めてはいるものの、やはり否定的なものである。それに対して Petrocchi は、原典に対するセルカンビのある種の自律性を強調する傾向があり、原典が作者にとって単に外的な機能しか持っていないとする。たしかに、この作品を完全なテキストで読む可能性が研究者に与えられたことは、物語の語り手としてのセルカンビのよりすぐれた評価のために役立つだろう。」⑯
⑯ Dizionario critico della letteratura italiana (diretto da Vittore Branca), Torino, 1974, Vo1.III, p.379 (Giuseppina Romagnoli Robuschi).
以上の一文は、セルカンビの評価の変動を示している点で私にはきわめて興味深く思われる。すなわちセルカンビはダンコーナ(1835~1914)のあたりの世代までは、暗黙の内に高く評価されていたが、やがてボッカッチオの臆面もない模倣者あるいは剽窃者として告発され、次に芸術的にも否定され、内容の卑猥、下品さのために軽蔑され、道徳的にも非難され続けた。ただ一点、誰も非難できなかったのはその資料的価値で、クローチェも「それを読む人は彼が保存し、蒐集して差出してくれるノヴェッラ的資料に感謝する」⑰ と述べ、サペーニョも「彼の本はむしろ比較ノヴェッラ学の研究者のためのすばらしい資料として重要さを持っている。つまり時には稀にしか記録されず、あるいはまさに全く記されたことのない物語的資料を大量に提供する。その一部は民話の口承的なレパートリーから吸収したものである」⑱ と評価している。
⑰ B. Croce, op.cit., P.95.
⑱ N. Sapegno, op.cit., P.357.
ところで、セルカンビ批評において注目すべきことは、この作晶の評価の下落が、イタリアのアカデミックな文学研究が整備され、近代的批評が確立されたのとほぼ時を同じくしたという事実である。まさにセルカンビは近代的な価値基準の成立と同時に、一挙に転落した作者だったのだ。
たしかにセルカンビの作品は、近代的なアカデミズムによって致命的と見なされうる欠点をいくつも備えていることは明らかである。それらの欠点を簡単に列挙すると、
(1)先ず近代批評がやかましく論じたオリジナリティの問題がある。この点に関して、後の構成の紹介でも触れるように、この作品はむしろ挑発的といって良い程の反則を犯している。話の枠組、作品中の詩句等々、借り物だらけの作品といっても過言ではない。しかも23篇にわたって、時には全面的に、「デカメロン」を踏襲している。
(2)セルカンビの文体に関しても、評価はきびしい。「彼の文体は全くなげやりでその叙述は心理的に深く追求することも、性格を浮彫りにすることもなく、単なる外的事実を伝えるだけである」⑲ という評価はほぼ定説化している。ただし率直にいってすでに現代の文学批評は「心理的追求」や「性格の浮彫り」をかって程重視しなくなっているのではないだろうか。むしろ「単なる外的事実を述べるだけ」という文体にある種の期待が感じられるのではあるまいか。
⑲ 注⑯ 参照。
(3)作品のまとまり、統一性、完成度などという点でも、セルカンビの作品は決して高く評価することはできない。しばしば矛盾を平気で犯し、折角オチがついた所で蛇足を加えることも多い。しかし作品をそのように静止した一個の芸術と見なす考え方は、記述された文学に固有のものであり、セルカンビ が半分浸っていた口誦文学の世界では通用しないものだったのだ。
(4)さらに内容が下品で、しばしば卑猥だという点でも、読者の反感を招き勝ちである。性的な描写のみならず、人肉料理や排泄物を用いた作品など、グロテスクな要素もしばしば扱われていて。嫌悪感をもたらすものとして非難されている。しかし実はそういう要素を抜きにして、この作品は語れないし、また真にこの作品を 代表する個性のある作品のいくつかがそういう要素を芯にして成立しているのだ。
(5)そうした内容から、ひいては作者の倫理感や道徳感にも疑問が寄せられやすい。その場合に、彼が「民主的自由の敵」であったという事実は明らかに影響を及ぼしている。たとえば先に引用したサペーニョのセルカンビの紹介にしてもある種の先入観を植えつけずにはおかないものである。小市民でありながら、独裁者に協力して栄達を求めたという汚名は、それだけで近代知識人の反感を招いた筈で、やはり評価の急激な下落の一因をなしているものと思われる。しかし実は作者が人民の敵であろうと味方であろうと、彼が書くノヴェッラの出来栄えには全く無関係である。
実はこの作品に下されている評価が、逆に作品そのものによってその限界を暴露されている可能性すらあるのだ。たしかに様々な欠点が目立ち、退屈でつまらない部分も少なくない(実はイタリア文学の古典の多くがそうなのだ)けれども、その中に何か否定し難いものが含まれていることだけは、いかに近代批評といえども認めざるを得なかった。といっても芸術的に否定している以上、「資料的価値」ということばですくい上げるより他に仕方がなかった。先に見た通り、クローチェもサベーニョもそうした面では最大限ともいえる讃辞を空している。
「資料的価値」とは便利なことばだが、私には不十分でやはり舌足らずなことばと思われてならない。実はそれはこの作品が蔵している「豊かさ」への感嘆のことばに他ならない。実際155(といっても1つは欠けている)のノヴェッラの内容の多様さは、それ自体一つの効果を形成しているように思われる。個々のノヴェッラのまとまりのなさ自体、欠点であると同時に長所でもあるのだ。後に見る通り、現代の大衆文学とも共通する一面が認められるが、そういう要素をアカデミズムや近代批評は一度もまともに評価しようとはしなかったのだ。イタリアの大衆小説の不振は、セルカンビのような作家を否定し続けたことへの罰ともいえるであろう。
さて最後に、セルカンビの文学を理解する上で特に重要だと思われる点をいくつか指摘しておきたい。先ずいくら強調してもし足りないと思われるのは、先ず彼の文学が地方都市から生れたということである。⑳
⑳ 内容豊かな興味深い論文であるが、C. Bec, Giovanni di Jacopo Sercambi et son《Novelliero》 は当然のごとくその著 "Le marchands ecrivains a Florence. 1375-1434, Paris 1967" 中の pp.175-198 に収録されていて、この作者をフィレンツェの文学者に仲間入りさせている。
ルッカはフィレンツェから徒歩でも無理をすれば1泊程度で行ける距離にあり、決して遠くはないが、すでに見た通りしばしば戦争状態にあったりして、今日考える程近くはなかった。だから勿論その刺激を十分受けてはいても、フィレンツェの文化水準と競争することなどは論外であった。フィレンツェのように文学愛好者や批評者の厚い層は望むべくもなかった。文筆を取る人にとって仕事はいくらでもあり、セルカンビは単独でヴィッラーニ家の人々の企てた年代記作りとボッカッチオやサッケッティの仕事とを両方抱えこんだ訳だが、それを十分理解し批評を加えてくれる人材は少なかった。だが後で見る通り、地方都市に住んでいたことが彼に独自の視点を与えたことは確実である。
その点に関連して、やはり決して忘れてはならない点は、当時の文化が今日からは想像し難いほど口誦性が強かったという点である。しかも更に厄介なことは、セルカンビが「主として口誦的な文化からもっぱら文学的で視覚的な文化への過渡」㉑ の時点に生きていたということで、しかもフィレンツェは文学の面ではまさに文字的で視覚的な文化形態の先進地帯であったという事実である。
㉑ John Larner, Culture and Society in Italy 1290-1420, New York, 1971, p.158.
地方都市であるルッカは、その変化において、フィレンツェよりもはるかに遅れていた。たとえば都会に生れ育った父親が、田舎で育った息子よりもはるかにモダンであることが見られるように、ボッカッチオはずっと遅れて生れたセルカンビよりも文化の推移に関して進んでいた可能性が大きい。セルカンビがしばしば非難される他人の作品の借用や模倣は、文字化された文化においては非難に値したが、口誦的文化の世界ではとがめ様もない事柄だった。その他数々の、今日にまでつながっている文字化された文化の約束事も、セルカンビにとっては、さほど切実な問題とはならなかった可能性が大きい。
第三に、セルカンビが一度も職業的文学者にはならなかったという点も忘れてはならないだろう。要するに彼の作品は旦那芸であった。今日彼の作品が蒙っている批評とは逆に、彼のノヴェッラは、披露されるとおそらく社交的讃辞しか受けなかったであろう。その点、文学者であることに自己の存在意義を見出していたボッカチオなどとは違う。結局セルカンビは言いたいことを言っておれば良かった。だから遠慮気兼なしに下品で猥せつな作品を発表することが出来た。彼のノヴェッラの中には、しばしば友情を裏切った独裁者の未路が描かれているが、それもおそらく彼の本音であるだろう。他にもいろいろあるだろうが、以上のような条件がもたらした影響は、現在のところ否定的な結果ばかりが注目されて取り上げられているが、その積極的な影響にも着目すべきではないかと思われる。
第2章 作品について
a. 『イル・ノヴェッリエーレ』の構成
作品の冒頭に10ページにわたる「序」の部分があって、1374年のルッカで、ペストを逃れるために一団の男女と聖職者が旅に出る計画を立てたことを物語る。彼らは団長を選出した。すると団長は会計係や世話係などを任命した後、ミサや娯楽についても適任者に依頼をし、道中の苦しさをまぎらわせるため、セルカンビを物語の話し手(altore 又は autore)に指名する。こうして指名された作者は、旅の途中や、宿先で、団長の求めに応じて物語を語り続ける。
以上がこの作品に収められた155(内1つはほぼ欠落しており、もう1つは半分しかない)のノヴェッラをまとめている枠組である。この枠組自体『デカメロン』の模倣であることは明白であり、作者自身「序」の締めくくり、『デカメロン』中のネイフィレのバッラータを借用していることからも明らかな通り、作者は模倣であることを隠そうともしない。しかもそれは原作よりもはるかに劣った模倣である。何故なら、デカメロンにおいては様々な男女が交互に語ることによって、単なる枠組とは呼びえないほどの様々な効果を発揮しえたのだが、本作品の場合は話し手はたった1人で単調極まりない上に、またその団体の旅の様子の描写などもはなはだ退屈だからである。
一応作者は旅の経路だけは記している。それによると、ルッカを出た一行は、ウンブリア地方やトスカーナ、ラツィオ地方を経てローマに入り、そこで10日間滞在する。それからナポリに向い、その地で3泊した後、長靴の先端レッジオまで足をのばし、さらに現在のターラントからブリンディジに至るが、バーリでペストがはやっているため、横にそれ、アスコリ等を経て、ボローニャに出、そこでも3泊する。その後はポー川流域で船に乗りヴェネツィアに向うが、そこでもペストがはやっていたためすぐに足を転じ、北イタリアの都市を巡回した後、ロンバルディーアを抜けて、ミラノでも1泊しただけで南下しルーニまで戻った所で中断している。しかしほぼ旅程は完成しているといえそうである。
ところで今見た旅の経路そのものが、実は Fazio degli Uberti の Dittamondo の中で行われた架空の旅の経路をそのまま借用したものなのである。おまけに、ノヴェッラの前文で、旅の宿で歌い手たちや聖職者たちが、カンツォーネやバッラータなどを歌って仲間を慰めたとして、しばしば様々の詩の断片が引用されているが、実はそれらの断片はほとんど全て、 N. Soldanieri を中心とする14世紀の詩人たちの作品の借用なのである。以上のように見る時、序文および名ノヴェッラの前文、つまりこの作品の枠組というべき部分には、ほとんど文学的価値はないと言っても過言ではない。またこのようにだらしのない構成である以上、この作品を一個の統一体として見る場合には到底高く評価するわけにはいかない。
しかしこのように安易でぶざまで、近代人の目にはがらくたとしか見えない枠組にも、若干の学ぶべき要素があることを忘れてはならない。先ず話し手が1人であることは、たしかにこうした書物の出来栄えにとってはマイナスの要素となる筈だが、ある種のリアリティを備えていることは否定しがたい筈だ。つまり現実に聴衆を楽しませる話し手の存在を考えると、10人の男女が10日間話し続けるよりも、1人の名人が聴衆を楽しませ続けることの方がはるかに現実的なのである。セルカンビの設定の方が、ボッカチオに比してずっと工夫が足りないようであるが、実はよりリアルな設定なのである。14世紀を文学の形態が、口承的なものから記述的、文字的なものに移行しつつあった時期と見なすと、ボッカチオなどはその移行の先端を進んでいた新しい文学の旗手であり、それに反してセルカンビはずっと古い形態を身にまとっていたといえる。つまり作者がここで自分自身として引受けた役割は、実は口誦的文学の世界の名人上手の残像なのである。
また一見単調な繰返しに見える前文の中に、口承文学がまだ生きている世界が存在していることを見逃してはならない。彼らは話し手のことばに夢中になり、入物たちの各々を愛憎の対象とする。さらに、そこで引用されているカンツォーネやバッラータは字面だけを読んでいても決して理解できないものなのだ。それらはほとんど常に「歌われた」ものだった。特にセルカンビが最も好んで引用する N. Soldanieri の作品は、まさに歌詞そのものであって、字面だけを読んでもらうために引用したわけでは決してない。セルカンビがあれだけ度々引用しているという事実は、まさに彼のそれらの歌に対する傾倒ぶりを証明するものに他ならず、この作品の持つ聴覚性の証明であるが、文字で読むだけではこの世界を味わうことは不可能なのである。
- 『イル・ノヴェッリエーレ』における各ノヴェッラの
舞台設定
イ. ノヴェッラの背景をなす時代
本作品の全体像を把握するために、先ずいかなる時代が各ノヴェッラの背景に選ばれているかを見ることから着手したい。ところが実際には、こうした作業をこの作品に適用することは、しばしば極めて困難であると共に、無意味でもある。その理由は、まず第一に、作者が執筆に当って、何時の時代の出来事かを明示することは少ないという事実にもとづいている。たとえば〈第三十九話〉は「フランス王ピピーノの時代に」という書き出しで始められるが、こういう例はむしろ稀であって、多くは場所は明示しても、時代についてはほとんど言及しない。そこでやむなく、登場人物からその時代を推理する他はないのだが、セルカンビの場合には一見歴史上の人物のように見えても決して油断はならない。
たとえば、〈第百二十四話〉 には messer Lancilotto da Ca Dandolo、〈第百二十七話〉 には messer Mafeo Orso という2人のドージェ(dogio)が登場するが、いずれも架空の人物である。ダンドロ家の4人のドージェには勿論 Lancilotto という人はいない。彼はフランス王を Filippo や、 Aluizi〔ルイ)、イギリス王を Riccardo などと呼びたがり、またイタリア諸都市を舞台にする時には、その代表的名家の人物を登場させる傾向がある。それは写実性を狙ったものとも、象徴的な表現だとも説明されるが、たとえば〈第十七話〉の Pulci、 Medici、 Perussi、 Asini 家の未亡人が一つの館に住んでいる話のような極端なケースになると、むしろ滑稽な印象すら与えるようにも思われる。
また一応は実在の人物が登場する場合でも、その時代が必ずしも明らかだとは限らない。たとえば、紀元前の人 Virgilio が、皇帝 Adriano (ハドリアヌス)の皇女に恋をするなどという〈第四十八話〉の場合、この物語が何世紀の出来事だったと見なすべきだろうか。さらに、こうした年代測定を全く無意味にしてしまうのは、作品中に時折見出される、女性の conno に口を利かせる話(第百四十一話)や、王女の腹中の蛙を追い出して王の後継ぎになる話(第百二十一話)など、あるいは〈第十四話〉〈第三十九話〉〈第百二十三話〉〈第百四十一話〉などのごとき純然たるお伽噺の存在である。大体これらの話を何世紀の出来事だろうと考えること自体ナンセンスであるが、実は日常の事件を語っている場合にも、セルカンビのノヴェッラには上述の fiaba と大差のない出来事が突然生起しうるのであり、その間に一線を画すことは不可能なのである。だから要するに、各ノヴェッラの作品の背景をなす時代を厳密に確定することは馬鹿げている。しかし一応の目安として、あえて各作品を時代別に分類すると次のような結果が生じる。
古代 バビロニア王国の時代 1
ダヴィデ王の時代 3
アレキサンダー大王の時代 1
ローマ共和政の時代 8
ローマ帝政の時代 2
中世以降
年代がほぼ推定しうるもの
1000年以前 4
1100年代 1
1200年代 4
1301~50年 18
1350年以降 25
年代の推定が困難なもの
かなり昔の出来事 18
ほぼ同時代と見なしうるもの 74
計 159
ただし〈第百五十四話〉は前文のみで欠落しており、その代り〈第二十四話〉は2個、〈第百十五話〉は4個の話で成り立っているので、序文も含めると合計(155-1+1+1+3=)159話となる。
すでに見た通り、こうした分類には無意味さがつきまとうのであるが、それにもかかわらず、我々が セルカンビの作品集の持つ性格を把握するのには、ある程度役立つ。先ず注目すべきは、ほとんど同時代の出来事と見て良い事件(14世紀以降の出来事)が117件、全体の74%、つまり約4分の3を占めているということ、またその内の6割強が日時なしに記されているという事実で、セルカンビはほとんどの事件と同時代の出来事として物語っているのである。
それに関連して注目すべきことは、彼が描く古代や中世初期の事件は、ほとんど同時代の出来事のように感じられるということで、ローマの元老院の出来事もルッカの長老達の集会の模様と大差はなく、デンマーク王の集団が船で渡来した姿も、彼ら自身の旅行の様子とほぼ等しい雰囲気で描かれている。つまり彼の作品には、歴史的意識がほとんど認められない。それを端的に示すのはアリストテレスとヴィルジリオの姿で、彼らの異常の能力に対する驚嘆はあっても、古代人の学芸に対する崇拝は認められない。つまりセルカンビは、近代人のような人類が進歩を続けているという未来に対する確信も皆無であると共に、ダンテなどに認められるような、過去のある時点に特に比重を置いて重視するという感覚もない。またそれ以上に重要なことは、過去との間隔をほとんど意識しておらず、古代に起こりえたことは全て現代にそのまま起こり得るものと感じている。ある時代の特殊性は意識されず、時間には全く濃淡が感じられない。だからあらゆる時間は、透明な普遍性を持っていて、そのため彼の作品は著しく共時的な性格を持っている。これは単に彼が歴史に無知であったという理由から生じた現象ではない。むしろそうした歴史的時間を無視した態度が、歴史への無関心と、ひいては時代錯誤を惹き起こしている。従って彼が政治的ノヴェッラを書く場合も、それは歴史というよりも、人間関係の図式として描かれ、彼の描くローマ史と同様、教訓もしくは珍らしい逸話に還元されてしまう。その点で fiaba の世界とも共通しているのだ。
ロ. ノヴェッラの舞台をなす場所
次に、各々のノヴェッラが背景としている場所について、一応の概括を試みてみることにしたい。先ずその作業に当って注目されるのは、時代の記述に関してあれほどルーズであったこの作者が、場所の記述に関しては驚く程の克明さを発揮しているという事実である。たしかに地名を示さずに物語を語ることは困難ではあるけれども、全作品を通じて、場所の不明なものは〈第十九話〉ただ1篇にすぎず、しかもそれとてたまたま冒頭の部分が少し欠落しているために我々には読めないというだけで、当初は作者によって明記されていたと考えるべきである。先に見た時代に関する記述のルーズさに較ぺると、やはりこの丹念さは注目に価し、作品の持つ空間的な性格を表わしている事実だと見なしうるであろう。
さて作品の舞台となる地名であるが、先ず、単独で事件の舞台を為すものは、次の通りである。
ルッカ 11
ルッカの郊外 Gello 1
同 Borgo a Mossano 1
同 Pescia 1
(現在はむしろピストイアに属するようだが、作者の判断に従う)
ルッカの郊外 Camiore 1
ピサ 13
ピサの郊外 Cuosa 2
ピサの管轄区(giudicato 1
(これはサルデニャーの可能性もある)
フイレンツェ 8
フイレンツェの郊外 Staggia 1
同 Empoli 1
(これはプラートよりもフィレンツェから遠いが、やはり作者の説明のことばに従って分類する。以下同じような、やや今日の地理と矛盾する場合には、同様に判断していただきたい。)
シエナ 2
ピストイア 2
プラート 2
アレッツオ 1
アレッツオの郊外 Montevarchi 1
同 Olmo D'Aresso 1
コルトーナ 1
サンミエアート 1
ルニジアーナの郊外 Vecciale 1
ルーニ(昔栄えた町) 1
フリニャーノ(モデナとの境界) 1
アペニン山中の Nicoli da Piuo]o 1
(以上ルッカ周辺〔一部エミリア・ロマーニヤ地方やリグーリア地方も含まれる〕とトスカーナの諸都市およびその郊外の小計)
57
ミラノ 3
ジェノヴァ 4
ジェノヴァ郊外 Corniglia 1
パルマ 2
パルマの郊外 Boera 1
ヴェローナ 1
ヴェローナの郊外 Palu 1
同 Marciano 1
同 Orsagliora 1
ボローニャの郊外 Bruscola 1
同 Castello del Vescovo di Bologna 1
同 La valle 1
フェルラーラの郊外 Torre della Fossa 1
ペルージァ 1
ペルージァの郊外(市の近くで地名なし) 1
同 Passignano 1
スポレート 1
スポレートの郊外(地名なし) 1
ヴェネツィア 9
ローマ 10
ローマの近郊(地名なし) 1
ヴィテルボ 1
ナポリ 2
サルデーニャの Arborea 区 1
(以上残りのイタリアの小計) 48
パリ 2
ブルゴーニュ 1
アルトワ伯領 1
Ghellere? 1
アヴィニヨン 2
ニース 1
ポルトガル 1
ナヴァール 1
(以上ヨーロッパ諸国の小計) 10
エルサレム 3
ベツレヘム 1
バビロニア 1
オリエント山岳地帯の入口 1
(以上東方諸国の小計) 6
計 121
次に2ヶ所以上の舞台を持つノヴェッラの場合を見ることにする(途中の道中も含む)。
先ずルッカと他の町を舞台とするものを列挙すると以下の通り。10
(ルッカ~ルッカ郊外Borgo、 ルッカ~コントローネ、ルッカ~ Bagno a Corsena、ルッカ~フィレンツェ(の道中)、ルッカ~ピストイア(の道中)、ルッカ~ヴェネッィア、ルッカ郊外の村Orbiciano ~シエナ郊外の村(地名記入されず)、ルッカ郊外の村 Diecinio~Borgo 、ルッカ郊外の村 Bargecchia~Schiva~Montemagno 、ルッカ郊外の村 Borgo~Pescia)
それ以外のイタリアの都市間にまたがるもの、またその道中。12
(ピサ郊外Massa Pisana~Vomo、フィレンツェ~ピサ、フィレンツェ~ピサ~ピサ郊外、ピストイア~その郊外6マイルの所、ピストイア~その郊外Poggio a Caiano、Siena~Viterbo、アンコーナ~ヴェネツィア、ボローニャ~その郊外、Milano~Venezia、Napoli~Toscana、Salerno~Reggio、サレルノのgiudiceの城~Castri)
次にイタリアと諸外国をまたがるもの。7
(フィレンツェ~ポルトガル、ボローニャ~ブリュージュ~アナルド(Hainau)~ボローニャ、バーリ~キプロス~Giffo(コルフ)、ジェノヴァ~コンスタンチノープル、ミラノ郊外~シャンパーニュ~パリ、バルセロナ~セヴィリヤ~ローマ、ミラノの郊外Panigale~アラゴン~シチリア~ナポリ)
外国間の各地にまたがるもの。8
(パリ~パリから80マイルの城、パリ~スペイン、ブルゴーニュ~ドイツ~パリ~フランス海岸の町、リヨン海~アドリア海~スペイン海〔作者の呼び方に従う〕、マケドニア~コズマル王の城、エルサレム~バビロニア~キプロス島、バビロニア~Campi di Soria(シリア)、Tanai~Mangi)
こうして2点以上にまたがるものは37にのぼり総計158(ただし155ー1〔第百五十四話〕ー1〔第十九話〕+3〔第百十五話〕+1〔第二十四話〕+1〔序〕)の背景を捕促しえた。
以上の表を見て最も注目に価することは、都市の周辺部の田舎町や村を舞台にする話が極めて多いということである。実は郊外という訳語では余り適切でないことも少くないと思われるが、作者は Contado di … という表現を好んで用いているので、それに従って機械的に修飾したわけで、むしろ領域位に訳すべき場合が多いと思われる。イタリアでは当時ヨーロッパの中で最も都市化が進み、しかも封建制国家とは性格を異にする、都市が周辺部を征服した形での領域国家が形成されていたのであるが、その結果あらゆる文化活動は大都市中心に進められ、周辺の小都市や村落はややもすれば取り残され、見落され勝ちであった。そうした中にあって、この作品がかなりの部分を、都市周辺の小都市や村落の生活を描くのに割いていることは何よりも注目に値する。
たとえば、作者の本拠地であったルッカを例に取ると、単独の舞台としてはルッカそのものが11に対して、周辺が4、複数の舞台を持つものでは、ルッカ自体が加わっているのが6、ルッカの郊外が関係しているものが8(Bagnoも郊外である)と、むしろ郊外の方が多く、全体では17対12という比率に達している。
他の都市に関してもそうした視点はある程度保たれており、都市がそれのみで成立している訳ではないことが忘れられていない。実はルッカ自体、度々外国の占領を体験するなど小国の悲哀をなめつくしている上に、文化的先進地帯ではなかったことが、こうした視点を彼にもたらしたものと思われる。この作品が、少くとも内容の豊富さという点では、辛らつな批評者たちからも高く評価されているのは、古い伝承を保ったまま新しい文化から取り残されていた周辺部との接触を、彼が当時の文学者たちよりもはるかに濃密な形で保っていた結果だと思われる。
またこの作者がかなり丹念に、事件の舞台となった村落の名前を拾い上げている点も注目すべきであろう。それはそれらの地名が、聞き手の興味を抱えた為だと思われる。今日でもイタリアの各都市は個性豊かだが、当時はそれよりもはるかに独自性を持ち一度通った人には忘れ難かった筈で、何の変哲もないような村の名前でも、おそらく我々には想像もつかない程の効果をもたらしたに違いないのだ。
さらにこの表で注目されるのは、ルッカが有している、ピサとフィレンツェに対する一種の三角関係である。さらにローマとヴェネツィアが多いことも興味深い。もっともローマは一連の古代伝説(すでに見た通り歴史とは呼び難い)の舞台となっているので当然だが、ヴェネツィアが多いことは注目に価する。逆に意外と少数なのがミラノである。ジェノヴァもヴェネツィアと較べて地理的近さを考えると意外と少ない。だがいずれにせよ、その数字が余り偏っていない点が興味深い。それから外国ではフランスが圧倒的に多い。その他のヨーロッパ諸国はほんの徴々たるものと言っても過言ではない。フランスは百年戦争で衰弱し、文化的にはフィレンツェを中心とするイタリアがほとんど圧倒しはじめていたのであるが、この作者の住んでいる世界では、まだまだフランスの文化的権威は高かったのだ。しかしそれも無理からぬことで、この作者が半ば生きている口誦的文学の宗主国はまさにフランスだからである。彼はそういう時代遅れであることによってその豊かさを獲得したのだった。
ハ、『イル・ノヴッリエーレ』に扱われた主題
さて、いよいよノヴェッラそのものについて触れる訳であるが、附録の部分であらすじを紹介すると共に、なるべくその要点と思われる部分には筆を割いておいたので、ある程度実物の面影は推定いただける筈である。そこで本論では、先ず代表作とされている作品や問題作を紹介すると共に、最もひんぱんに扱われる主題をいくつか取り上げて、漠然とではあるが、この作品の大体の輪郭を紹介しておきたいと思う。
すでに前章で引用した文章にも見られたように、この作品中で最も好意的に受け入れられて来たのは、「民話的および喜劇的」な性格のノヴェッラであった。事実そうした作品は興味深いものが多いようである。たとえば L.Rossi が註釈の途中で特に賞讃を加えている作品は、〈第五十九話〉の義兄と関係した娘が妊娠してしまうが、病気だと称して姉や婚約者をだまし、無事に子供を生んで里子に出した後、まんまと婚約者と結婚する話と、〈第百一話〉の何も知らない牛飼いの少年と少女が、未亡人の母親たちの示唆で性行為を覚え、やがて結婚する話で、前者は「最も生彩に富む作品の一つ」とされ、後者は「独創的な新鮮さで描かれている」とされている。前者はとも角、後者はたしかに最高の出来栄えを示しているといって良さそうである。
また〈第百三十三話〉の40年後に戻って来た友人のために、家や財産をそっくり準備おいてやった商人の話は、この作品中最も有名(la più celebre )なノヴェッラだともされている。なお全作品中最も長いのは、〈第百三十九話〉のイギリス王子がフランス王の叔父のもとで育てられ、その嫉妬のために馬丁をやらされるが、変装してスペイン王のトーナメントに出場しその王女と結婚するという、かなり民話的色彩の強い作品である。途中からフランス王の態度が突然改まったわけが少し良く分らないが、波乱万丈の騎士道物語と称しうるものになっている。
それに対して、従来最も非難の的になってきたのは、〈第百八話〉のアヴィニヨンで生じた人肉料理事件のてん末記だと記されている。つまりある泥棒上りの男が、教皇庁があるおかげで繁昌しているアヴィニヨンで料理屋を開いたが、美味なのと元手がただなのとに目をつけて。死刑にされた死体の肉を切って来て店に出し、大当りを取ったという話で、その時の作者の平然たる筆致がけしからぬとされて来たそうである。しかし作者が実際に食ったわけでもないし、別にそれ程目くじらを立てることもあるまいというのが、率直な印象である。それどころか、私にはこのノヴェッラはこの作品の一つの側面を典型的に代表している珍重すべき作品だと思われるのだ。
ところで、この作品中最も頻繁に現われるのは、あるいは当然のことかも知れないが、男と女の関係を描いたノヴェッラである。というと余りにも漠然とした言い方かも知れないが、若い男が娘を襲い(第五話、第六話)、男は妻の浮気封じに工夫をこらし(第七話)、その努力も空しく妻はあっさりと浮気してしまい(第七話)、伯爵夫人が商人に売春を持ちかけて犬の糞を手に入れ(第八話)、修道士たちが商人の女房にほれて店まで押しかけて殺されてしまう(第十話)、などといった唯ならぬ出来事が、全作品の半数近く〔今挙げたのは第一話~第十話の間のものだけである)すなわち約70編に起っているのである。Masuccio の作品では女性をめぐる争いは、一種の階級闘争に還元することも可能だったが、この作品ではそういう見方はほとんど無理で、まさに男と女とが性別闘争を起している、また時には大饗宴を催しているという印象を受ける。聖職者といえども、欲望に駆られて必死のなぐり込みをかけているという印象を与えることが少くないのだ。
それに次いで多いのは、広義の犯罪事件である。もし姦通や売春をもその内に数えるならば、過半数が何らかの形で犯罪に関係していると見なすことも可能だろう。しかしそこまで語義を拡げなくとも、本作品中に登場する泥棒、詐欺師、海賊の総数は、何らかの特定の職業のどれにもまして多数に及ぶ。しかも犯罪を犯すのは彼らだけに限らないので、その件数は一そう増えるのである。たとえば詐欺だけを取ってみても 第八話、第九話、第二十一話、第二十二話、第五十五話、第九十話、第九十八話、第百五話、第百十一話、第百四十六話等々、まだ他にもあるかも知れないが、その手口は多種多様で巧妙である。
それに対して、犯人を捕える側の巧みさを描いた作品も少くはない。そうした捕物の例を挙げると、第十八話、第十九話、第二十話、第二十二話、第八十八話、第八十九話、第九十一話等々は、いずれも巧みな推理によって犯人を捕えた例である。また裁判そのものもそうした犯人探しの場である。そういえばこの作品が、そうした犯人探しの審判を第1話に据えていることを無視してはならないだろう。ここで注目すべきことは、多くの場合彼らの犯人探しが理詰めで行われているという事実である。騎士道物語の系統には、決闘によって黒白を決めた例もないではないが(たとえば第三十九話、第百三十一話)、そうした例はむしろ例外で、すぐれた判事たちは先ず推理し、その後で必要に応じて拷問をかける。
だから先に挙げた〈第十八話〉以下の作品群や、裁判物は推理小説の先駆と見ても、決して見当違いではあるまい。なお裁判ものの中には、ソロモン王の知恵を描いたものが3篇まじっているが、そのことからも分るように、こうした興味は古代から常にある程度存在しており、決して近代人だけに固有のものではなかったのだ。しかし奇跡や神の裁きに依存したり、拷間が勝手気ままに用いられる社会では、そうした興味は萌芽のままに止まるであろう。セルカンビの文学の中では、当時としては珍らしくそうした推理小説的要素が多少の発達を示している。それは彼の住んでいた社会にある程度の近代的性格があったことを示しているのであるまいか。
その他の主題は先の二つに比較するとずっと少ない。たとえば、彼の多数のノヴェッラの中には、当時の政治情勢を扱ったものも若干ある。その内の1つの主題は、コムーネ制の政体の実態を描いたもので、かってのアンツィアーノ(長老)たちが勝手なことをするのを、すぐれたリーダーが改革する話(第百七話)、ある高慢なアンツィアーノがトイレに尻がくっついて立てなくなってしまい、大騒ぎをした結果態度を改める話(第百十三話)、アンツィアーノになった靴屋に酷使された市庁舎の下僕が、靴を買いにいって仕返ししたが、結局罰せられた話(第百十九話)など、いずれもルッカ以外の出来事として描いてはいるが、ルッカでも十分起りうる事柄である。最後の話では、作者は当然靴屋に味方しているとされている(Rossi)が、その全てから感じられるのは、民主政体に対する一種の幻滅感もしくは諦念のごときものである。
もう一つの主題は、一度支配者の地位につくと、それまでの与党を裏切って敵方と和解し、結局仲間から孤立して失脚する独裁者の悲劇である(第百三十五話、第百三十六話、第百三十八話等、第百四十四話も類似)。それはそれぞれピサ、サンミニナート、ニースの事件として描かれているが、全く同じ話といえるほど(ニースの場合はあとに話が続いているが)、その要旨は似ている。これらを読む時、この作者が持っていた党派心の強さに驚かされ、作者からは忘恩の徒と罵倒されてはいるが、敵方と和解して亡命者の帰国を許す独裁者にむしろ同情したくなる程である。しかしその確信の強さや、断固とした。迷いの全くない判断を読んでいると、その心情が極めて根強いものであることがわかる。それと共に、民主政体が成立した後にコムーネが体験せねばならない党派争いの激烈さもあわせて実感させるのだ。これが当時の現実なのだと痛感せざるを得ない。
彼のノヴェッラには、貴族と民衆の対立をまともに描いたものは意外と少ないように思われる。勿論、〈第六話〉のフリニヤーノ伯のように、息子が未亡人の娘を犯し、父親が抗議に来た未亡人を犯した挙句、好き勝手なことばを口走るなどといった、怪しからぬ封建貴族もいないわけではないが、逆に手に剃刀を持った床屋からいろいろな物をねだられ、その時は何でも素直に聞いてやり、後で品物を取りに来た床屋にあげる訳にはいかないと(極めて柔和な態度で)断わる封建領主の姿も描かれている(第七十二話)。そして前者の舞台がフリニャーノ、後者の舞台がルッカの郊外の村とされているのを知る時、ここに地域差によって生じるある種のリアリティを感じざるを得ないのである。
セルカンビの魅力は、全篇ことごとくそうだとは言い難いけれども、しばしば細部にみとめられるこうしたリアリティの魅力だといえそうである。そういえば、〈第九十六話〉と〈第九十七話〉に描かれたフィレンッェ貴族の傭兵なども、興味深い存在である。ことに、戦さにいく途中、うんこの山を怖がってその度に立止まるトロンバ・デイ・サルヴィアーティの姿などはまさにセルカンビの文学でしかお目にかかれない独自のもののように思われてならない。彼はあるいは民主的自由の敵であったかも知れないが、民衆が見たものや語り笑ったものを、おそらくどの作家にも劣らず書き残しておいてくれたのではないだろうか。男と女の関係(それもかなり卑猥に描かれている)といい、犯罪の実話や体験談といい、それらは確かに今日の大衆小説の主題とかなり重なり合っているように思われる。しかし同時に、そこにはこの時代の民衆でなければ見えなかったことが記録されているのである。
彼がしばしば取上げる汚物、死体、陰茎、あるいは寝呆けた亭主が卵と間違えて飲んで女房に笑われる間男の精液などといったものは、口承文化を活気づけるのに不可欠なリアルな要素だったのであり、それらを下品だとか俗悪だなどと切り棄てたところに、今日にも及ぶイタリア大衆文学の衰弱の原因がある。それらの要素を排除してしまうと、ここに描かれた男女関係は一挙に色あせてしまい、電圧は下ってしまうに違いないのだ。
それと共にもう一つ注目されるのは、日常的、ニュース的要素の多いことである。若い時の体験談をはじめ、直接の見聞談にもとづいているものも時折見られ、口承文化の世界が、一方ではソロモンの知恵や騎士道物語をも保存しつつ、他方では新しい題材を取捨選択してある種の新陳代謝を行っていることが推察されるのだ。
こうして書き残された作品には、すでに何度も指摘した欠点を補って余りあるものが含まれている。具体的にいうと、全作品中40編余りに対して、L. Rossi は「文学的前例不明」もしくは「年代記的(実話的ととれる)断片」などという注釈をほどこしており、つまり作者が記述しなければ今日には残らなかった話なのである。そしてその中には、すでにその一部を指摘した通り、単に「資料的価値」などということばによって過去の遣物視してしまえないものが、含まれているものと確信する。
第2章は作品から抜き出した一覧表をもとにして書いたが、その表は省略しておく。なお本論はあくまでセルカンビ の作品の紹介の目的で記したものなので、冗漫な附録を添えることをお許しいただきたい。